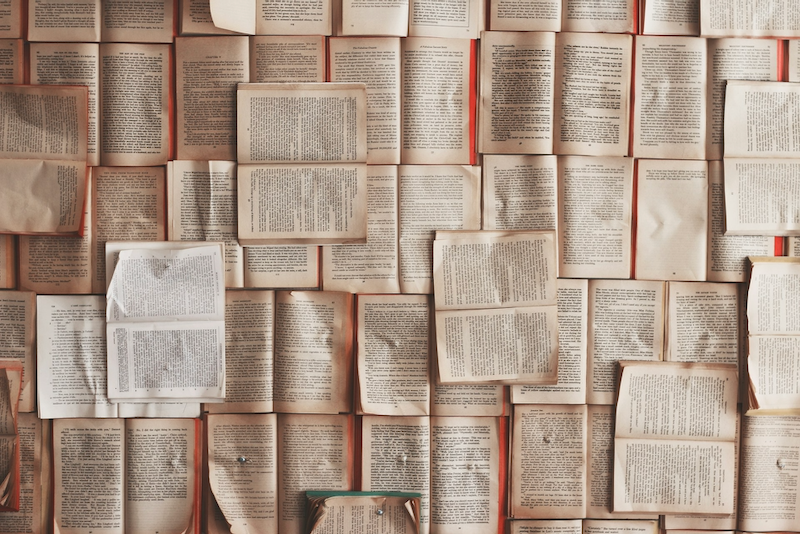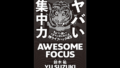ひとつの記事にしにくい本をまとめてレビューする「ミニレビュー」のコーナーです。
「メモはカードで取ったら生産力があがるよ」みたいなことをちょっと前に知って、でも詳しく調べずに放置していました。で、最近また同じような情報を目にしたので関連書籍を3冊ほど読んでみました。
ノートは「情報カード」で取る
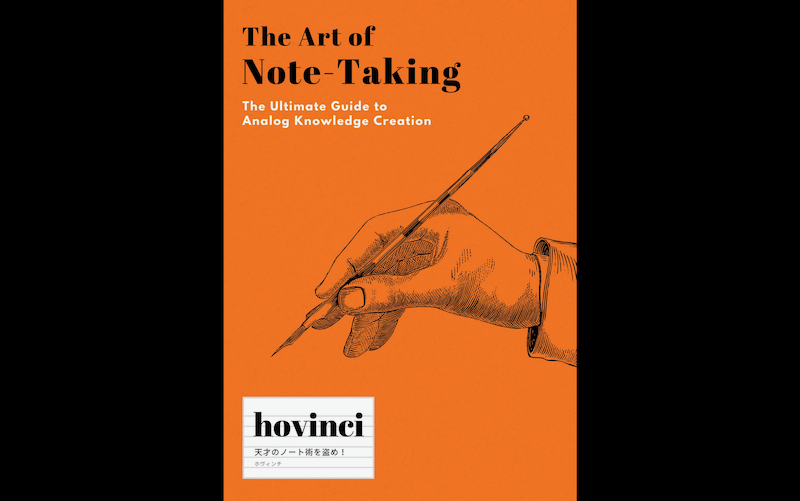
【天才のノート術を盗め!】は、「ノートは情報カードで取ろうぜ」という主張を3人の具体的事例から主張している本です。
普通のノートでノートを取るのと、カードでノートを取る違いは
- アイデアの順番を入れ替えるのが簡単
ということでしょうか。カード1枚あたり1つのことしか書かないようにして、過去に書きためた情報カードを眺めてみたり、順番を入れ替えたりしてみてアイデアを作るそうです。
梅棹先生の試行錯誤の記録
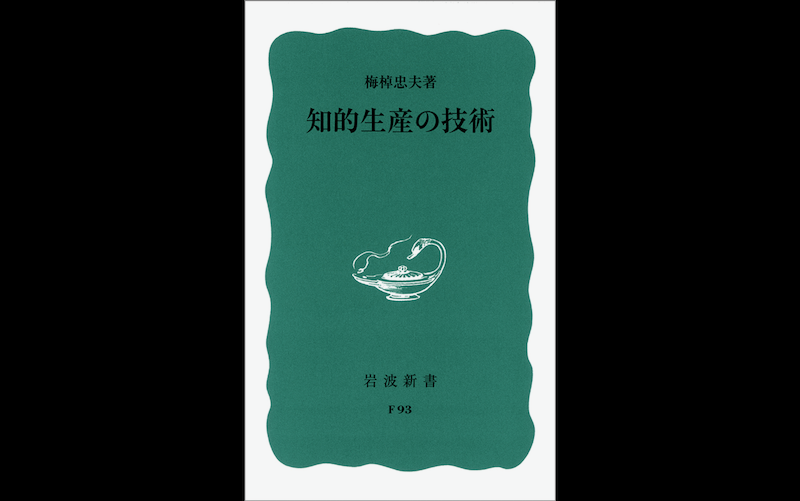
【天才のノート術を盗め!】で最初に紹介されていた梅棹忠夫先生の著書【知的生産の技術】も読んでみました。
1969年に書かれた本なのですが、コンテンツを作ったり、情報を整理したりすることの基本的なことが書かれています。
基本といっても世間の共通認識の基本というよりも、梅棹先生がメモや書類管理、整理について試行錯誤してきた歴史が書いてあるのがおもしろいです。大先生もでいろいろ思考錯誤してるんだなっていうのが印象的でした。
梅棹先生のおもしろいところは、自分が使いやすいようにカードや収納キャビネットを発注していたそうで、それが世の中に広まっていて「京大式カード」と商品化されていったそうです。
僕も梅棹先生に倣って、京大式カードを買ってみましたが単行本サイズでけっこう大きめ。でも持ち運びにはそこまで気にならないし、1つのアイデアや情報を書き込むには困らない大きさです。
書きためたものを寝る前に一通り目を通すだけでも記憶の定着に良さそう。そして記憶に定着するということはアイデアが生まれやすい土台を作るってことですから、しばらくやってみようと思います。
「ツェッテルカステン」を詳しく解説してある本
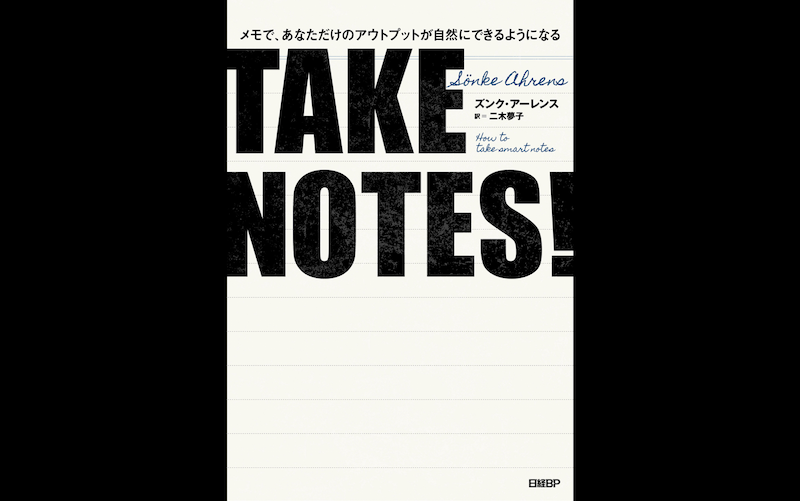
1960年代、ドイツのニクラス・ルーマンという人が実践し、体系化した「ツェッテルカステン」を詳しく解説した本がこの【TAKE NOTES!】です。
「メモをノートではなくカードにとる」というのは梅棹式と同じですが、もっと細かく体系化してあるのが「ツェッテルカステン」です。
ただこういうハウツー系にありがちなのですが、正直わかりにくいというのが本音。画像もちょっとあるだけで、具体的な実践例がとぼしいので、イメージがつかみにくいです。
なので「ツェッテルカステン」というメソッドをそのまま使うというよりは、使えそうなところだけをかいつまんで使いつつ、だんだん理解していくのがいいのではないでしょうか。番号を振るとか、分類して箱に入れるとか、けっこう面倒くさそう(シンプルな方法って主張はされていますが…)。
まとめ
実際にノートではなく、カードにメモを刷るという方法を実践してみていますが、これ自体はかなりいい感じだと思います。まだ数十枚しかないから管理をしなくてもいいっていうのもあるかもしれませんが、ノートに書くと閉じてしまうので、開かないと中に書いてある情報は取り出せません。ただカードだとすでに情報が外に出ているので、カードを「くる」だけでいいっていうのはけっこう使いやすいと思います。
個人的にはカードに書いて毎晩見返し、覚えてしまったり、体に染み込んだりしたら捨てるっていう方法をとっていけば、カードが増えすぎずにいいのかなって思ってます。あとはアイデアとしてアウトプットしてしまったりしたら。