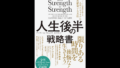集中力がもたないという問題はもはや現代病みたいなもので、無関心でいるわけにはいかない問題だと思います。
学生のころを思い出してみるとけっこう長時間集中していた記憶があるのですが、今は30分も何かに没頭していることを思い出すことができないくらいです。
個人的にはスマホなどの誘惑が増えたことは原因のひとつだと思うのですが、だからと言ってスマホを手放すわけにはいきません。この状況で僕たちは元の集中力を取り戻すことができるのでしょうか?
今回紹介するのは、鈴木祐著【ヤバい集中力】です。
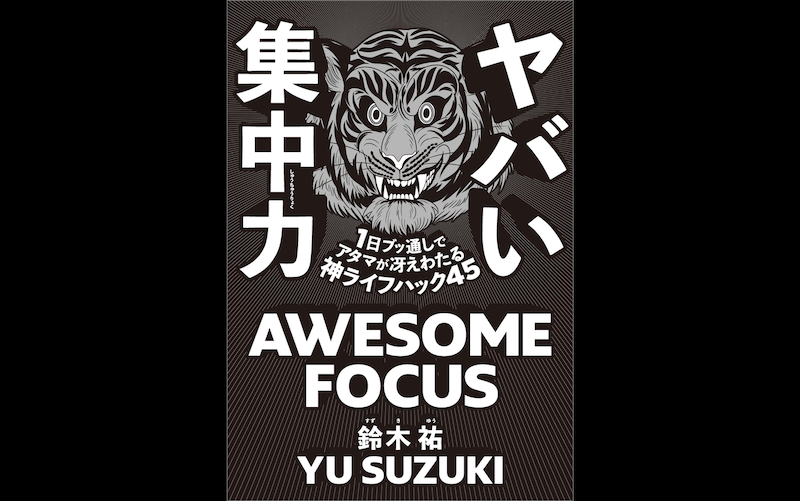
【ヤバい集中力】によると、脳の中の「獣」を飼いならすことでとんでもない集中力を発揮することができるそうです。
脳の中の獣ってどういうことなのでしょうか? そして獣を飼いならすってどういうことなのでしょうか?
この記事では【ヤバい集中力】を要約し、気になったところを解説していきます。
脳には「獣」と「調教師」がいる
誰もが「あのときは頑張れたのに今日頑張れないのはなぜだろう?」と考えたことはあるでしょう。自分という人間は一人なのに、自分の性格やモチベーションが日によって変わるのはなぜだろうと僕も思ったことたくさんあります。
人間の脳っていうのは、理性を司る領域と本能を司る領域があり、そのせいで一人の人間に二つの人格があるように感じます。これを【ヤバい集中力】では「獣」と「調教師」と表現しています。
獣が本能、調教師が理性です。例えば目の前にお菓子があって「食べたい!」と思うのが獣で、「でも食べたら太るよ」と理性的な行動を促すのが調教師です。
「獣」と「調教師」のメタファーのとおり、いくら調教師と言えど、獣をコントロールするのは難しいです。調教師は様々なテクニックを使って獣をコントロールしなければいけません。
そのテクニックを学べるのが【ヤバい集中力】ということです。
記録を反復し、継続する
獣をコントロールするためには、獣のことを知らなければいけません。獣の特性の一つに「反復に強く反応する」というのがあります。
原始時代は現代よりも過酷な環境で、不確実性に満ちた世界でした。そんな中で「この木には果実がなっている」とか、「このタイミングでここにいけば獲物がいる」みたいな「反復されたできごと」に注目するように人間は進化しました。
なので人間は何度もくり返されるものに魅力を覚え、反復に対してモチベーションが高めるようにプログラムされているのです。
その文脈で「儀式(ルーティン)」の話に展開されるのですが、僕がおもしろかったのは「記録を反復する」ということです。
例えば、最近僕は「野菜を食べた日」を記録しているのですが、記録を継続することにより脳内の獣が「野菜を食べることは大事なことに違いない」と思い始めます。野菜がずっと嫌いでしたが、記録して確認し続けることで「野菜を食べることは大事」と脳に植え付けるのです。
それからさらに記録を継続すると、「こんな大事なことを継続できている自分はスゲー」となり、自己効力感がアップするのだとか。
記録もカレンダーに○をつけるくらいでOKなので、こんなに簡単に自信が身につくならやるべきでしょう。
「小さな不快」トレーニングを行う
集中力がないのは「不快に耐えるだけの力がない」ということで、不快に耐える力を鍛える必要があります。
不快に耐える力を鍛えるには筋トレと同じで、自分に負荷をかければいいのですが、いきなり大きな負荷をかけると潰れてしまいます。なので、最初は小さな不快に耐えるトレーニングをしましょうということです。
小さな不快とは例えば「仕事に飽きたと感じたら、あと5分間だけ続けてみる」みたいなものです。作業を中断したくなったらとにかく「あと5回」とか「あと5分」とか続けるだけでも集中力が鍛えられるし、生産性もかなりアップするそうです。
僕の場合だったら、読書の集中が切れたときに「あと5分」とか「あと5ページ」とかよさそうですね。とにかく「やめたい」と感じたらあと5分だけ頑張るっていうのを続けてみたいと思います。
まとめ
【ヤバい集中力】によると、脳の中の「獣」を飼いならすことでとんでもない集中力を発揮することができるそうです。
なんとなく集中力というものを捉えていても、的確に集中力を鍛えることはできませんが、獣と調教師というフレームワークで考えると、効果的に集中力を上げることができますよね。
巻末には実践ロードマップもあるので無理なく集中力フィックスができるように設計されています。現代人にとって必読の書と言えるでしょう。