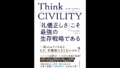読書をするようになっていろんな知識が入ってくると「学校教育」に対して疑問がたくさん生まれてきます。
学校教育で行われている施策はエビデンスベーストなものが少なく「この校則はなんだろう」とか「もっとこういうふうにすれば学力は上がるのに」と思うことが増えました。
事実、学校教育は他の分野と比べ進歩が遅く、大昔から形状が変わっていない「傘」と同じだと揶揄されることも少なくありません。
今回紹介するのは、中室牧子著【「学力」の経済学】です。
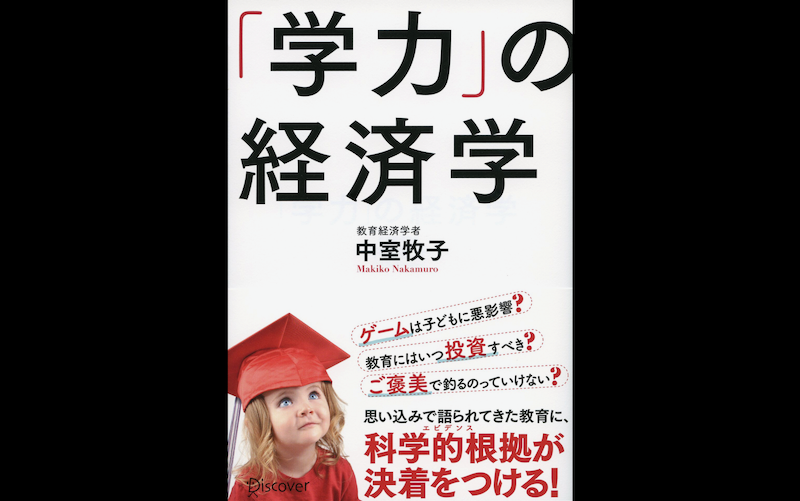
【「学力」の経済学】では、学校教育の施策について「経済学」の視点で切り込んでいます。ようするに「その教育で子どもたちの将来の収入がどれくらい変わるのか」を指標としています。
もしかしたら「教育は金じゃない」とか言い出す人もいるでしょうが、それは現実から目を背けているだけです。現実問題、多く人は将来困るから受験をし、できるだけ良い学校に入ろうとしているわけです。
最近では学歴と年収の相関はだいぶ低くなってきたようですが、ただ闇雲に教育をするよりも何かの指標に基づいて考えていくほうがいいことは疑いようがないでしょう。
この記事では【「学力」の経済学】を要約し、気になったところを解説します。
「ご褒美に効果はない」はウソ
子どもに勉強をやらせたいというときに「ご褒美には効果がない」と聞いたことがある人は多いでしょう。ただ「なぜご褒美に効果がないのか」ということを掘り下げないと、薄い知識を貪っているだけで、本質に辿り着くことはできません。
まず子どもが本心からやりたいと思ってやっている活動、内的モチベーションがMAXの場合は、ご褒美を与えてはいけません。もしあなたの子どもが「勉強楽しい!」と自発的にやっていたらそのまま見守るのが重要です。
しかし、ほとんどの子は勉強が好きではないでしょう。でも宿題とかしなければいけない、テスト勉強はしなければいけないとなったときに、ご褒美は効果を発揮するのです。
具体的には
- 宿題が終わったら、すぐにご褒美を与える
という方法が提案されています。ご褒美の種類についても書いてあったので、それは本書でご確認ください。
これは抽象度を上げると「インプットに対してご褒美を与えている」ということになります。ここで間違ってはいけないのは「アウトプットに対してご褒美を与える」のはNGということです。
アウトプットとは、例えば「テストの成績」ですね。「80点以上取れたらご褒美を与える」みたいなことはダメということです。
これやってる人意外と多いのではないでしょうか。もしやっている人がいたら、インプットに対してご褒美を与えるという方法に切り替えてみてください。
しつけを受けた子どもは、将来の年収が86万円高くなる
各種SNSを見ていると、若者の礼儀やマナーを嘆いている投稿が多いように感じます。おそらく礼儀やマナーのようなトピックは多くの人に関心が多いテーマなのでしょう。
【「学力」の経済学】でも、しつけを受けた人は将来の年収が高くなるということが書かれていました。
しつけというのは具体的には
- ウソをついてはいけない
- 他人に親切にする
- ルールを守る
- 勉強をする
というような基本的なモラルで、そこまで理解が難しいことではありません。このようなしつけを子どものころに受けた人と受けなかった人とでは、年収に86万円の差があったそうです。
なぜこのような結果になるのかというと、しつけを受けることで子どもの勤勉性(誠実性)が高まるからだそうです。確かにこれは経験的に、感覚的にわかることですよね。
ただ当たり前ですが、行き過ぎたしつけは子どもを壊すので要注意です。そのあたりは【「叱れば人は育つ」は幻想】みたいな本を読んでみてください。
いき過ぎた平等主義が格差を拡大させる
日本の教育は平等主義すぎて、一時期「手をつないでみんなでゴールしましょう」という運動会がメディアに取り上げられていました。
その光景を見て、違和感を感じた人も多いはず。実際に「いき過ぎた平等主義は格差を拡大させる」というデータが出ているそうです。
世の中というのは理不尽で、生まれたときから平等ではありません。そのような現実から目を背けているのが「いき過ぎた平等主義」です。現実から目を背ければ背けるほど、他人を思いやり、親切にし合おうという気持ちがなくなってしまうのだそうです。
まあよく考えたら「いき過ぎた平等主義がヤバい」ってことくらいは容易に想像はつきます。現実的に世の中は平等ではないのですから。平等主義で生きてきた子どもたちは、現実の荒波を乗り越えることは非常に難しいでしょう。
人生がずっと理不尽はさすがにきついですが、長い人生の中で理不尽な出来事はいくらでもあります。そのたびに親が寄り添って支えてあげる、教育のいい機会としてあげればいいでしょう。
まとめ
【「学力」の経済学】では、学校教育の施策について「経済学」の視点で切り込んでいます。ようするに「その教育で子どもたちの将来の収入がどれくらい変わるのか」を指標としています。
我々が日本全体の教育について考えることはあまり意味がなく、まずは自分の家庭において【「学力」の経済学】の知見を利用してみるのがいいと思います。
闇雲に突き進んでいくのではなく、経済学的な指標という目標に向かっていくことで、今よりは良い教育をすることができるようになるのは間違いないでしょう。