僕は今までの人生で「自分にはセンスがない」と考えて生きてきた人でした。
運動のセンス,ファッションセンス,色彩のセンスなど,ある人がうらやましいと思って生きてきました。
「センスは生まれつきの能力」と考えると,これからの人生も希望がありません。
しかし,もし後天的にセンスを身につけることができるとなれば最高です。
今回紹介するのは,水野学著【センスは知識からはじまる】です。
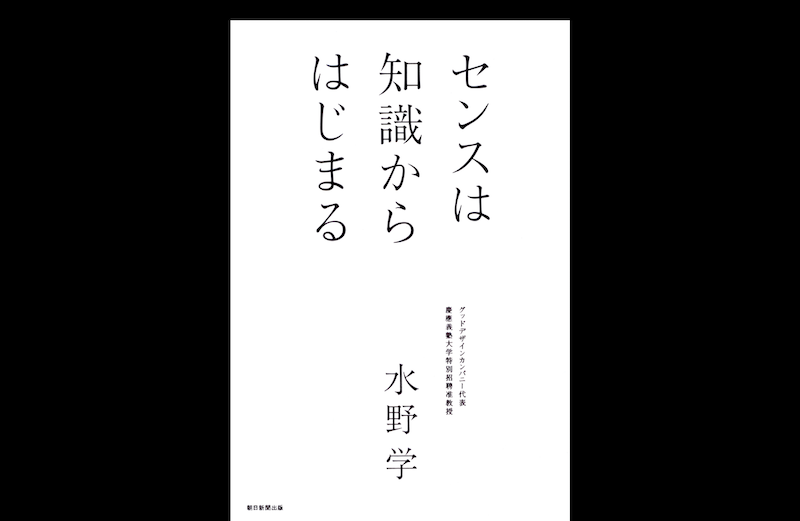
【センスは知識からはじまる】によると,センスとは「最適化する能力」であり,生まれつきに備わっている能力ではないと書かれています。
それを聞くと希望が見えますが,ではセンスの正体はどんなもので,どうやって身につけることができるのかが気になるところです。
この記事では【センスは知識からはじまる】を要約し,気になったところを解説していきます。
センス=最適化
センスを語る上で,まずはセンスを定義しなければいけません。
【センスは知識からはじまる】ではセンスを以下のように定義しています。
数値化できない事象の良し悪しを判断し,最適化する能力
すごくいい定義ですよね。
しっくりきます。
例えば,自宅に友達が来たとき,夏だったら冷たい麦茶を出したり,冬だったら暖まるお茶を出したりしますが,これが「センスがいい」ということです。
逆に「センスがない」だと,365日水道水を提供してしまうようなことですね。
そのシーンにあった行動ができていない=最適化していない=センスがない,というふうに考えればいいかなと思います。
「ファッションセンス」を考えると,流行の服を着ていることよりも,自分に似合う服を着ていることだったりします。
センス=最適化と捉えると,今自分がやっている行動はセンスがいい行動かなと考えることができますよね。
見え方のコントロールをする
センス=最適化とすると,「見え方のコントロール」もセンスですよね。
例えば,すごく美味しい料理を出すレストランがあるとします。
シェフの技術も最高,素材も最高,当然,料理も最高です。
しかし,その料理が盛りつけられている食器がダサかったらどうでしょうか。
もっと言えば,レストランの内装も料理がよく見える内装ではないとか,カトラリーも使いづらいとか食べづらいとか。
これも最高の料理を提供するというシーンの最適化ができてない状況です。
どんなに最高な料理でも見え方のコントロールができていないと,お客さんに響きません。
僕自身もそうですが,見え方のコントロールができない人って多いですよね。
それはおそらく几帳面さとか観察力も必要なのだと思います。
自分のサービスがどのように見えているのか,それをもっと考える必要がありますね。
感覚や好き嫌いに頼らない
「センスがいい」と自称している人が感覚的に仕事をしていることってよくありますよね。
【センスは知識からはじまる】では,これを明確に否定しています。
センスというのはあくまで知識の集合体で,客観情報が重要だと書かれています。
その中で感覚や好き嫌いは知識や客観性と真逆のものです。
例えば,ベルギーチョコレートのパッケージを考えるときでも,使用するフォントを感覚や好き嫌いで選ぶのと,「ベルギーチョコレートだからベルギーで生まれたフォントを使おうか」と考えるのとではまったく違うということです。
その知識をもとに仕事をしないと,クライアントから「なんでこのフォントなんですか」と聞かれたときに答えられませんよね。
僕なんかは逆に感覚が疎いので,最初から知識を使って仕事してしまいますね。
例えばロゴを作るときには「コンセプト的にYouTubeのロゴの色を使いたいから,調べよう」となります。
これが「センス」だったんですね。
今まで自分にはセンスがないと思っていましたが,もしかしたら逆だったのかもしれませんね。
まとめ
才能とかセンスという言葉を使う人は「生まれつきの能力」という意味で使うことが多いはず。
しかしセンス=最適化と考えると,センスはスキルであることがわかります。
センスを生まれつきの能力と考えてしまうと,それがなければ厳しいですが,スキルと考えると身につけることができるものです。
どちらが真理として正しいではなく,自分の人生にとってどういうふうに考えたらいいのかというほうが大事だと思います。
「センス=最適化」であり,スキルであるから身につけることができると考える人生でいこうと思いました。


