僕も人の親なのでわかりますが,我が子のことに関しては期待も大きいですが,不安も同じくらい大きいように思います。
学校での成績や素行が悪かったり,何をやらせても続かなかったり,このままでは将来ろくな仕事に就けず苦労するのではないかという不安を持つ親御さんは多いでしょう。
どうやったら「よい子育て」ができるのかという具体的な問題もそうですが,そもそも「いつ教育投資をするべきか」という,教育効率が高くなるのはいつかということを知らない人も多いでしょう。
今回紹介するのは,ジェームズ・J・ヘックマン著【幼児教育の経済学】です。
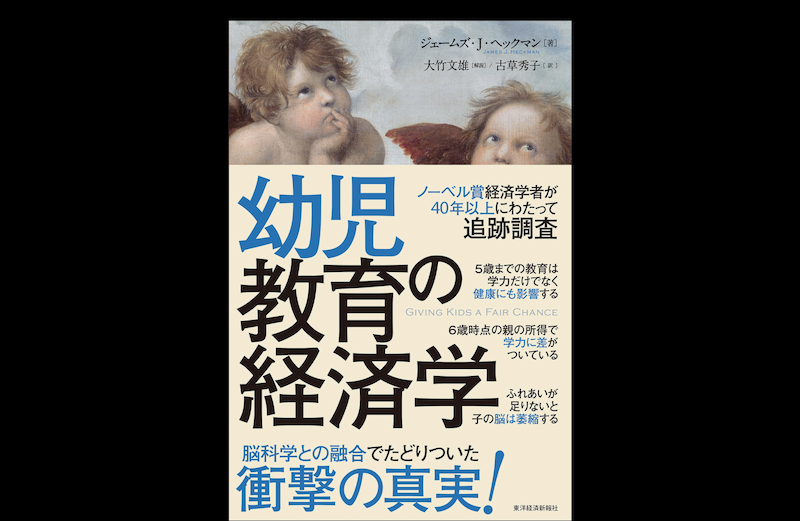
【幼児教育の経済学】によると,就学後の教育の効率性を決めるのは,就学前の教育にあるとのことです。
こういう結論を聞くと「じゃやすでに小学生の我が子は手遅れってこと?」と思う方もいらっしゃるでしょう。
確かに,小さいころのほうがいろんなものの影響を受けやすいことは間違いないでしょう。
教育もそうでしょうし,スマホなどの悪影響なども子どものころのほうが影響を受けやすいのは確か。
ただそれは「効率」を考えたときの話で,成長したあとでも教育の効果というのは十分に発揮します。
【幼児教育の経済学】は,その「就学前の教育」というのがどういうものであり,それは生涯に渡って重要なことなので,十分に役に立つ内容だと思います。
この記事では【幼児教育の経済学】を要約し,気になったところを解説していきます。
家庭環境を強化する
最近では日本でも「親ガチャ」という言葉があるように,遺伝子による議論をする人は少なくならない印象です。
ようするに「自分の能力が低いのは無能な親の遺伝子を受け継いだからだ」という主張なのですが,こういう議論は時代遅れなのだそうです。
エピジェネティクスという考え方があるのですが,これは環境によって遺伝子のスイッチがONになったりOFFになったりするという考え方です。
例えば,反社会的な行動や犯罪率の高さと関連する遺伝子は,虐待を受けるような厳しい環境で育つことによりスイッチがONになることが明らかになっています。
遺伝子か環境かという考え方ではなく,遺伝子と環境は相互作用するという考え方が主流なのです。
日本ではなじみがないかもしれませんが,海外だと今日の夜に食べるものにありつけるかどうかも不安な人たち,家に帰っている途中で銃で撃たれてしまわないかと心配しながら生きている人もたくさんいます。
そのような安心できない環境で育っていると,人生に悪影響を及ぼすような遺伝子のスイッチがONになりやすいというわけなのです。
研究データを見てみると,どうやら幼少期からそのような環境で育っていると,小学生になったとき,大人になったときに社会になじめず,問題行動を起こしやすいみたいです。
だからこそ,幼少期に介入を行い,家庭環境を強化する必要があるのです。
親は収入を上げるように努力する
日本の貧困率のデータを見ると,1980年代では60歳以上の高年齢層のグループの貧困率が一番高かったのですが,1990年代から徐々に子どもの貧困率が上がってきています。
2000年代になって貧困率が一番高いのは,なんと5歳未満の子供たちのグループだったそうです。
その背景にはその親である20〜30代の貧困率が上昇しているからなのだとか。
ということは,幼稚園や保育園に我が子を通わせることができない家庭が増えている,または今後どんどん増えていくということで,就学前の教育ができる環境がなくなってしまいます。
親の所得と子どもの学力の相関は,日本でも見られると言われています。
こういうデータを見て,親として僕ができることは,「黙って収入を上げる努力をしろ」ということでしょうか。
SNSで「父親が無知なら貧乏になる」という言葉をみて,確かにそうだよなと思ったことを覚えています。
お金がすべてを解決するわけではありません。
【幼児教育の経済学】の中でも「貧困家庭にお金を配るだけでは解決しない」と書かれています。
ただ,子どもが安心して生活できるための基盤は,やはりお金だと思うわけです。
収入を上げる努力をしたり,投資により資産を守ったり,親はお金の勉強はしたほうがいいと思いました。
まとめ
【幼児教育の経済学】によると,就学後の教育の効率性を決めるのは,就学前の教育にあるとのことです。
幼少期というのはいろんな影響を受けやすい時期なので,結論としては妥当かなと思います。
だからといって,すでに小学生以上だから手遅れかと言うとそんなことはありません。
確かに幼少期のころよりは苦労するかもしれませんが,親としてやるべきことが「子どもが安心できる環境を提供する」ということはずっと変わらないわけです。
介入する時期も大事ですが,基本的な子育ての方針が定まっているということのほうがはるかに大事だと思いますので,ぜひ参考にしてみてください。


