このブログでは【超一流になるのは才能か努力か?】とか【初心にかえる入門書】のように「スキルを効率よく身にけるためにはどうすればいいのか」ということを教えてくれる本をたくさん紹介しています。
どれも素晴らしい内容なのですが、「じゃあその練習方法でどこまで上にいけるの?」という具体例はあまり紹介されてないので、「この本信じていいんか?」と思うこともあるかもしれません。
今回紹介するのは、ジョッシュ・ウェイツキン著【習得への情熱】です。
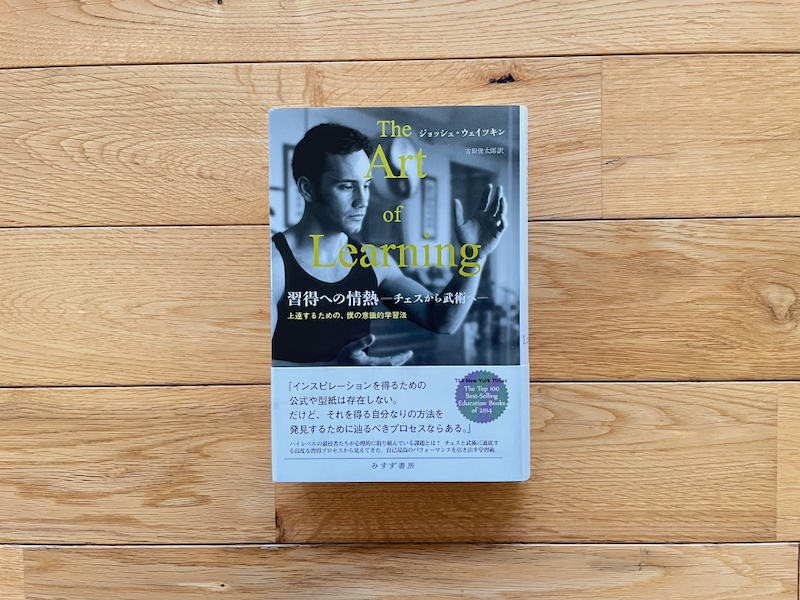
【習得への情熱】の著者であるジョッシュ・ウェイツキンさんは、若いころはチェスの世界チャンピオンになり、その後、太極拳を始めて、太極拳でも世界チャンピオンになったという異色な経歴の持ち主。
一方では頭を使った競技で、もう一方は体を使った競技。相反する競技で両方ともチャンピオンになった秘訣は才能ではなく、「技術を身に付ける術を知っていたから」だということです。
内容はウェイツキンさんの体験談ではありますが、その他のスキル習得系の本の内容と照らし合わせても相違ない内容なので、意図的な練習の成功例として捉えることができます。
この記事では【習得への情熱】を要約し、気になったところを解説します。
複雑性を排除した局面の練習をする
【習得への情熱】の中で一番心に残っているのは「複雑性の排除」という考え方です。
例えば初めてチェスを学ぶとき、教えるのが下手な先生はいきなり全ての駒を使いながら教えるそうです。でも全ての駒を一気に使おうとすると、脳がパンクしますよね。全ての駒に配慮をしなければいけないので意識は分散し、一つひとつの駒に関する理解は浅くなります。
教えるのが上手い先生はまずは「キング」と「ポーン」(将棋で言えば王将と歩)だけを使い、その2つの駒の動き方や役割などを教えていき、それが体に染みついてきてから初めて、ビショップの駒を追加して教えていくそうです。
このように複雑性を排除し、まずは学ぶ対象をシンプルにし、習得できたらそれを複雑な局面に適応させていくほうが習得も速くなるし、深く学べるそうなんですね。
で、ウェイツキンさんはこのチェスの学習法を太極拳にも応用しています。
太極拳の技で複雑で難しいものがあるらしいのですが、それをよく観察したら5〜6段階で成り立ってるということに気づいたそうなんです。そこまでわかったらそれぞれの段階を一段階ずつゆっくり動きながら何度もくり返し、慣れてきたら全ての段階を統合してまた何度も練習をくり返すそうなんです。
一見、難しそうなものって大枠で捉えてしまうと圧倒されて「これを覚えるのは無理だな」ってなりますけど、観察して分解することでシンプルになり、取っつきやすくもなるし、そっちのほうが理解も速いっていうのは覚えておいて損はないでしょう。
スローモーションで練習する
上記の「複雑性の排除」とも関連してくる内容ですが、複雑性を排除し、シンプルな型に分解したあとには反復練習をすることになります。
その反復練習は「まずスローモーションでくり返す」ということが推奨されています。どれくらいスローモーションかというと「お茶を注ぐように」と表現されていました。なんと美しい表現なのでしょうか。
一つのスキルを5段階まで分解したとして、その一段階ずつをスローモーションで練習することになるのですが、当然時間がかかりますよね。でもそれでいいんです。
だいたいスキルが身につかない人の特徴って「焦っている」んですよね。速く習得したいから練習も汗って速くやってしまうことが多いでしょう。まるで腹を満たすためだけに立ち食い蕎麦屋に入って蕎麦をかき込むように練習をしています。
そうではなく、練習は「コース料理」のスピード感でやらなければいけません。一品ずつ料理が出てきて、それをしっかりと味わって次に行く。これくらいのスピード感で練習したほうが長期的に見ても得なんですね。
中庸を探究する
【習得への情熱】の中に「学習とは中庸の探究である」と書かれていました。
例えば、何かを極めようとするのであればハードな練習は必要です。でも、あまりにもハードすぎる練習をしすぎて怪我をしたり、バーンアウトしてしまったらいけません。
過程を重視するからと言って、勝利にまったくこだわらないのもダメだし、新しい自分になるためには今の自分を捨てなければいけないかもしれないけど、全部捨ててしまったらダメだし。
というふうに、どちらかに極端に振りすぎるのではなく、その間、中庸を目指すべきだということなのです。
僕の場合、怪我をしたくないからちょっと練習をゆるめにすることが多いので、もう少し追い込んでもいいのかなって反省しました。何でもどちらかに傾倒しすぎたらダメなんだなということを肝に銘じたいと思います。
まとめ
【習得への情熱】は、著者であるジョッシュ・ウェイツキンさんが、チェスと太極拳の世界チャンピオンになった過程が書かれている本です。
もし何かに伸び悩んでいるのであれば、読んで見て損はないでしょう。たくさん心に刺さる表現があると思います。
また【超一流になるのは才能か努力か?】みたいな本も一緒に読めば、お互いを補うように理解が深まるでしょう。


